連載コラム「株の始め方」
-
- 第19回
株式分割銘柄で注意することとは?
【権利落ちとは】
3月になると、多くの企業が決算時期を迎えます。決算のときには、株式分割や配当金支払いの権利の付与によって、株価が下がることがあります。これを権利落ちといいます。
今回は株式分割について説明したいと思います。
株式分割とは
たとえば、「3月末時点の株主に対して保有する株式の数をタダで増やしてあげますよ」という株式分割(無償増資)などがあると、価値が下がったわけでもないのに株価が下がったこととして計算されます。1株1000円の株に対して1対2の株式分割をすると、1株が2株になるわけですから、理論上は1株500円が適正株価ということになります。(会社の価値は変わらないので株数が2倍になれば、株価は1/2になるはずです。)
「1株1000円の株を1株持っていた」株主は、「1株500円の株を2株持っている」という状態に変わります。見た目の株価では1000円が500円になるので損をしているように見えますが、株数が2倍になっているので実際の価値は分割前と変わりません。つまり、見た目の株価では損しているように見えても、株主は、実際に損しているわけではないということです。
権利落ちとは
ただし、“3月末時点の株主”にはタダで株式の数を増やしてもらえる権利があるのに対して、その翌日に1株500円で株を買って株主になった人にはこの権利はついていません。このように、権利をなくした分だけ株価が下がることを「権利落ち」といいます。
最近では、大幅な株式分割を行う企業も増え、その場合の適正株価も大きく下がってしまうことになりますので、いろいろな注意が必要となってきます。
効力発生日とは
さて、「平成18年(2006年)1月4日以降を基準日とする株式分割から、基準日の翌日を効力発生日とする」との制度改正が行われています。
旧制度では、株式分割で新しく発行される新株の株券が流通するまでに約2ヶ月かかっていました。つまり、新株の売買はしばらくの間できないという状態でした。そのため、株が品薄状態(2倍の株式分割の場合、流通している株式数が1/2となっているため、分割前よりも株数が少ない→品薄状態となるためです。)となりそれを狙って投機的な売買がされることもありました。
新制度では、証券保管振替機構(ほふり)に株券を預けている場合、基準日(株主名簿で確定される日)の翌日が新株の効力発生日となり、この日から新株の売買が可能となります。このように、新株を売買できるようになるまでのタイムラグを少なくしたことで、株の品薄状態による株価の急激な上昇は抑えられます。
また、これに伴い、株式分割による新株券の発行日決済取引が行われないことになりました。
【権利落ち前後の信用担保の評価】
信用取引の担保にしている株式が分割した場合は、代用有価証券として取り扱われますが、株価は権利落ち後の親株券の株価となり、株数も権利落ち後の株数になりますので、実質的に評価額は変化しません。
詳細は各金融商品取引業者(証券会社)で変わることがありますので、取引きされる金融商品取引業者に確認されることをお勧めします。
[コラム執筆者]
時川郁(ときがわふみ)ファイナンシャルプランナー(CFP)
証券会社に勤務後、FPとして活動。運用・投資に関するiDeCoや企業型DC、NISAなどのセミナーを中心に、若者やリタイアメント世代向けのライフプランセミナー、個別相談業務、執筆などを行っている。
「人生100年時代を豊かに生きるための手助けを!」との思いから、2016年に合同会社リテラビットを設立し、確定拠出年金の導入コンサル、導入支援事業を始める。趣味はスポーツ観戦とゴルフ、ドライブ、おいしいものを食べに行くこと。
- 口座開設
-
トレジャーネットでの口座開設費用・管理料は無料です。
- 関連リンク
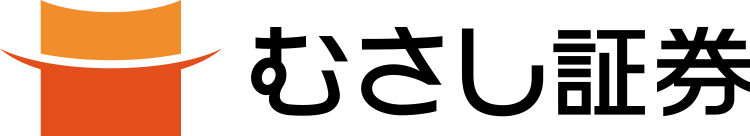
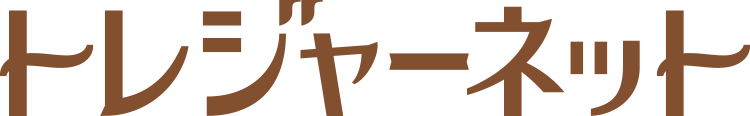
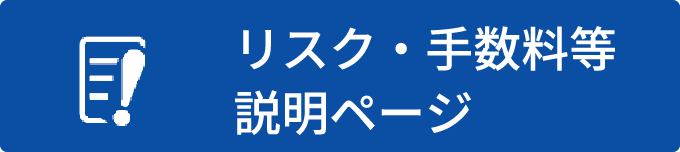
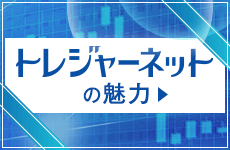

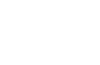 0120-972-408
0120-972-408
 048-643-8367
048-643-8367