連載コラム「株の始め方」
-
- 第15回
ETFとは?<ETFの概要について解説>
ETF(Exchange Traded Funds)とは、「株価指数連動型上場投資信託」のこと。「上場」は、取引所で取引できることを指しますから、一般の投資信託(インデックスファンドなど)と違って、取引所で売買可能な投資信託のことです。2001年7月から取引されるようになりました。
【ETFの種類】
ETFは、東証株価指数TOPIXや日経平均株価などの国内の株価指数や業種別株価指数、NYダウ、SP500、NASDAQなどの海外株価指数、その他国内外の債券、商品その他の指数に連動して運用される銘柄が、2024年7月9日現在295銘柄あります。購入や売却は、通常の株式と同じく金融商品取引業者を通して行い、指値注文や成り行き注文ができます。また、信用取引も可能です。
【ETFの数】
2024年7月現在、日経平均連動型が10本、TOPIX連動型が9本、東証1部上場の銘柄のうち時価総額や流動性の高いJPX日経インデックス400連動型が7本、その他1部上場の電気機器や輸送用機器銘柄、銀行の株価指数など業種別株価指数に連動するものが17本が取引きされています。購入単位は1株、10株、100株、1000株などがあり、5万円程度から投資できます。
【ETFと一般の投資信託の違い】
では、一般の投資信託と比べてETFにはどんな違いがあるのでしょうか。
まず、一般の投資信託はその投資信託を取り扱っている金融機関でしか購入できませんが、ETFは全国の金融商品取引業者で注文ができます。
売買するときの価格は、普通の投資信託は1日1回決定される基準価額。基準価額は売買した後に確定することが多いので、思い通りの価格で売買することは困難です。それに対して、ETFは株式と同じようにリアルタイムで値動きします。成り行き注文はもちろん、指値注文で希望の価格を指定することができます。また、価格がいくらになっているかも、一般の投資信託は日経新聞やインターネットで確認する必要がありますが、ETFは株式と同じように4桁の証券コードが付けられていて、株式と同じようにいつでも確認できます。また、新聞の株式欄にも掲載されます。
【ETFのコスト】
コストについては、一般の投資信託は、購入手数料(0〜3%程度)と保有時にかかる信託報酬(0.5〜2.0%程度)が必要です。(信託報酬が0.1%程度の投資信託もありますが、ほとんどが日経平均等インデックスに連動するタイプです。一般の投資信託なので1日に1回決まる基準価額での取引しかできません。)
それに対して、ETFの売買は株式と同様に委託手数料がかかり、保有時のコストは一般の投資信託より低いものが多く国内指数連動タイプで0.3%(±0.2%)程度となっています。海外指数等連動商品では、多少割高になりますが、NASDAQ連動タイプでは0.6%前後、中国株指数連動タイプでは0.96%程度のものなどがあります。(銘柄によって違いがあるので必ず確認してください。)
【ETFの税金】
ETFの税金の取扱いも株式と同じで、特定口座・NISAの利用が可能で、特定口座であれば一般の株式との損益通算も可能。分配金も株式の配当金と同じように所得税が源泉徴収されます。
ETFはTOPIXや日経平均やその他の指数に連動するので、毎日のニュースでだいたいの値動きを把握することが可能です。
株式と同じように取引きできる利便性と、少額で幅広い銘柄に分散投資できる投資信託のメリットを兼ね備えた商品、それがETFだと言えるでしょう。
[コラム執筆者]
時川郁(ときがわふみ)ファイナンシャルプランナー(CFP)
証券会社に勤務後、FPとして活動。運用・投資に関するiDeCoや企業型DC、NISAなどのセミナーを中心に、若者やリタイアメント世代向けのライフプランセミナー、個別相談業務、執筆などを行っている。
「人生100年時代を豊かに生きるための手助けを!」との思いから、2016年に合同会社リテラビットを設立し、確定拠出年金の導入コンサル、導入支援事業を始める。趣味はスポーツ観戦とゴルフ、ドライブ、おいしいものを食べに行くこと。
- 口座開設
-
トレジャーネットでの口座開設費用・管理料は無料です。
- 関連リンク
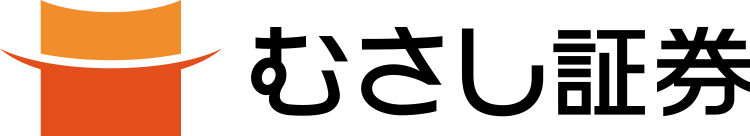
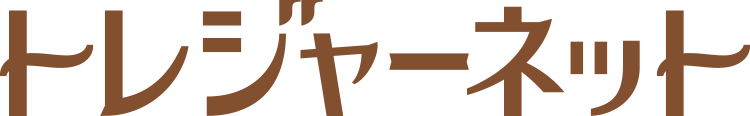
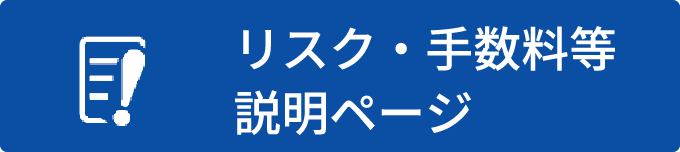
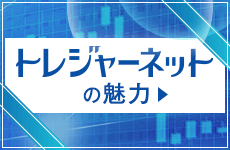

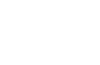 0120-972-408
0120-972-408
 048-643-8367
048-643-8367